
| 「戦場からの証言」証言者の兵歴 |  |
|
| |「戦場からの証言」証言者の兵歴|太平洋戦争年表|地域別の戦闘・作戦|主要海戦航空戦地図| | ||
| 陸軍:工兵・通信兵 | 中国:安慶、岳隊、常徳、衝陽等〜湖南省宝慶(終戦) |
|
◆久田 二郎さん |
■生年月日■:1920年(大正9年) |
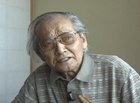 ◇初代朝風の会代表 取材日:2005.06.27 |
|
|
|
|
| 【第116師団】
|
戦場証言 |
|
1941年(22歳)応召 |
|
| |
|
|ページトップ| |
| |